みなさんこんにちは!
さつま骨格矯正の高木です😊
最近は気温も下がってきて、少し秋らしくなりましたね🍂
季節も変わり目には、体も順応しようとして疲れも出やすくなるので、気をつけてください。
さて今回は、食いしばりと内臓についてのお話です。
「夜になると顎がこわばる」
「朝起きたら、エラが疲れたり肩こりがひどい」
そんな方は、内臓の疲れと自律神経の乱れが関係しているかもしれません。
顎や咬筋(エラの筋肉)といった外側の筋肉の緊張は、
実は内側の臓器の状態を映していることがあります。
内臓と筋肉は筋膜や神経でつながっており、どちらかが緊張するともう一方にも影響が及びます。
その橋渡しをしているのが「自律神経」です。
● 内臓が疲れると、交感神経が働き
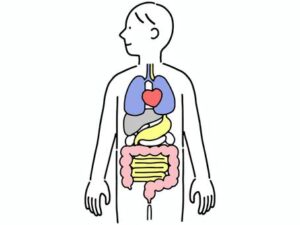
内臓が疲れていると、体はその不調をカバーしようとして交感神経(活動モード)が優位になります。
この神経は緊張・集中・ストレス反応を担うため、常に身体を“戦闘モード”にしてしまいます。
本来、夜になると副交感神経(リラックスモード)が働くはずですが、
交感神経が強く働き続けると、筋肉が常に緊張したままになってしまうのです。
その結果
・寝ている間もエラ周りが休めない
・無意識に食いしばってしまう
・朝起きると顎や首、肩が重い
といった症状が起こります。
● 内臓の不調が体の硬さに現れる
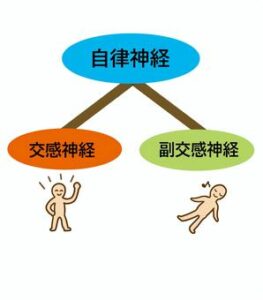
内臓はすべて自律神経によってコントロールされています。
例えば、
・胃腸 → 副交感神経が活発になると動きが良くなる
・肝臓 → 交感神経が働きすぎると硬くなり、肩や顎の筋緊張を引き起こす
・腸 → ガスや便秘で圧が高まると、横隔膜の動きが制限され呼吸が浅くなる
こうして内臓からの信号が筋膜を通して胸・首・顎の筋肉へと伝わり、
結果的に「内臓の硬さ=体全体の硬さ」に直結します。
● 食いしばり改善には、骨格と内臓の両面アプローチを

食いしばりを改善するには、筋肉をほぐすだけでは不十分です。
骨格を整えることで内臓の位置関係が正しく保たれ、
それによって自律神経のバランスが整いやすくなります。
骨盤や肋骨、背骨などを本来の位置に戻すことで、
内臓も自然と「働きやすい環境」を取り戻します。
その結果、副交感神経が優位になり、体の内側からリラックスしやすい状態に変わっていくのです。
食いしばりは、単なる癖ではなく体の中からのサインです。
「内臓の疲れ → 自律神経の乱れ → 筋肉の緊張 → 食いしばり」という流れを理解すれば、
本当に必要なのは“リラックスできる体づくり”だと気づけるはずです。

