こんにちは!渋谷院の堀内です。
今回は食いしばりが起きやすくなる環境や条件についてお話ししていきます。
食いしばりやすくなる要因
1、ストレス
2、習慣
3、姿勢
4、噛み合わせ
5、子供特有のもの
などとさまざまな要因があります。 これらをひとつずつ詳しく説明していきます。
1、ストレス
脳や体が精神的、肉体的ストレスを感じると体が緊張しやすくなってしまい、自律神経が乱れる原因にもなります。
自律神経が乱れると交感神経と副交感神経の切り替えが不安定になり、交感神経が優位になるので食いしばりやすい状態になってしまいます。
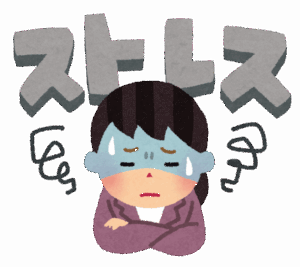
2.習慣
食事の際に、右ばっかりで噛んでしまっている人は右側のお顔の緊張が強くなってしまいます。
また、ガムやグミなどや硬いものをよく食べる場合も同じ現象が起こりやすくなってしまいます。
これらの習慣は食いしばりにつながるだけでなく、お顔の左右差の原因にもなってしまうため、日頃から左右どちらでも噛めるように意識すること、硬いものなど食べ過ぎないようにすることが必要になります。

3.姿勢
スマホの普及やデスクワークなどにより現代社会では姿勢が悪くなってしまう要因が多くあります。
不良姿勢には反り腰、猫背、ストレートネックなどがあります。
これらは顎を引く姿勢になってしまうので、上下の歯が当たりやすくなり食いしばりにつながります。
面長感や食いしばりが強くなる原因のひとつに姿勢があるので、外観だけではなくお顔の症状の改善のためにも姿勢改善が必要になります!
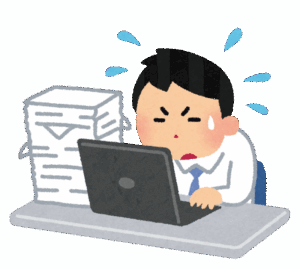
4.噛み合わせ
・開咬(オープンバイト)
・過蓋咬合(ディープバイト)
・反対咬合(受け口)
などの不正咬合は奥歯にかかる負担が多いため、食いしばりやすくなったり、食いしばりが強くなったります。

5.子供特有のもの
成長過程で子供の食いしばりはよく見られるものですが、乳歯から永久歯に生え変わる時期の食いしばりは歯並びに影響しやすくなります。
一般的には自然に治ることが多いですが、長時間の歯ぎしり、6歳あたりを過ぎても歯ぎしりがある場合、痛みが伴う場合は治療が必要になることもあるため注意が必要です。

食いしばりやすい要因についてお話しさせていただきました。
気になることがあった方はぜひ1度当院にご来院いただいて、ご相談や歪みの検査・診断・施術の方を受けていただければと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました!

