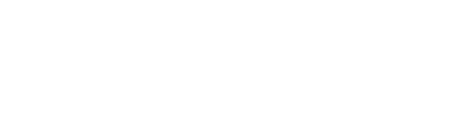こんにちは!柔道整復師の堀内です。
今回は総院長が出版した ” 90秒あご筋ほぐし “ からむくみに関するセルフケアについてお話させていただきます!
顔のむくみは、前日のお酒や塩分の摂りすぎのせいだと思っていませんか?
実はもっと大きな原因は、あご機能の停滞です。あごの周りには老廃物を体の外に排出するリンパがたくさん集まっています。
あごの機能が低下すると、あご周りの血管を圧迫してしまい血液やリンパの流れが滞り、余分な老廃物や水分が顔に蓄積してむくみ顔に😨
特に夏は冷房のかかった部屋にいたり、冷たい飲み物を飲むことが増えたりするので更にむくみやすくなっています。
下あごとむくみの関係
あご周りを押すことで刺激されるのが、耳下腺・舌下腺・顎下腺の3つの唾液腺です。
特に、耳下腺は全体の23%もの唾液を生成するので重要なポイントです💡
また唾液腺の周囲にはリンパ節も集まっているため、あご下を押すだけで、顔のむくみの元になる余分な水分や老廃物も排出され、むくみを解消することができます。
🌟やり方
あごの先から耳の下まで、手の位置を少しずつずらしながら、親指であごの下のたるみを骨の下に入れ込むように、5回押し流します。

🌟リンパの悪循環からくるむくみをオフ
左の鎖骨のくぼみは鎖骨下リンパ節といってリンパ液の出口となるところです。
ここをしっかり押して解放することで、体内の余分な水分が排出され、むくみにくくすることができます。
🌟やり方
右手の人さし指、中指、薬指を左の鎖骨のくぼみにあてる。指を押し込むように垂直に圧をかけて、リンパ節を5秒押す。反対側も同様に行います。

🌟背筋伸ばし+舌出しでむくみオフ
長時間同じ姿勢でいると全身の筋肉が硬くなってしまい、血流が悪くなることが原因でむくみを引き起こしてしまいます。
顔のむくみやたるみと深く関係しているのがスーパーフィシャルバックラインと呼ばれる、背中・首の後ろ・後頭部・額まで繋がる筋膜です。
猫背などが原因で背中の筋膜が伸び切った状態になると、顔の筋膜がゆるんで顎に老廃物が溜まってしまい顔がむくんで大きくなります。
顔のむくみを取るには、正しい姿勢は必要不可欠です。
正しい姿勢で背中の筋肉が伸縮すれば、背中から顔の筋肉を引き上げて、むくみのない顔になります💡
🌟やり方
背筋を伸ばして立ち、利き手で反対の手首を掴み、後ろに引っ張る。
同時に顎を上げ、舌を思いっきり上に上げて30秒キープ。手を入れかえて反対側も同様にやります。

このようにむくみにフォーカスしたセルフケアもたくさんあるんです💡
セルフケアは症状に合わせて様々ございますので、当院に通われて患者様にはそれぞれの症状に合わせたものを指導させて頂いております🎵
セルフケアは毎日の積み重ねが大切です🌟
コツコツ頑張っていくようにしてくださいね☺️
最後までお読み頂きありがとうございました!
ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください💡